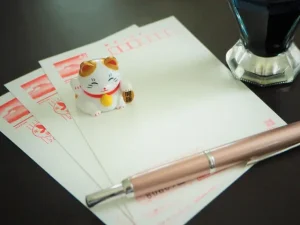お盆の帰省で親戚の子どもたちと顔を合わせる際、「お盆玉」について頭を悩ませていませんか。
近年耳にする機会が増えたこの習慣ですが、そもそもお盆玉はあげるべきですか、と疑問に思う方も少なくありません。一部では迷惑だと感じる声もあり、そのいつからの発祥や、もし渡す場合の相場がいくらなのか気になるところです。また、いざ渡すとなれば、お盆玉の書き方や入れ方、新札の準備、いつ渡すかというタイミング、さらにはお返しやお礼の有無、何歳までが対象なのか、現金ではなくお菓子で代用するのはどうなのか、など考えるべき点は多岐にわたります。
この記事では、「お盆玉をあげない」という選択肢はありなのかという疑問に正面からお答えし、お盆玉の基本知識から実践的なマナーまで、網羅的に解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。
- お盆玉をあげないという選択肢があること
- お盆玉の由来や歴史、基本的な知識
- 年齢や関係性に応じた相場や金額の目安
- 渡す場合に失礼にならないためのマナーや準備
お盆玉をあげない選択肢と基本知識
- お盆玉はあげるべきですか?
- そもそもお盆玉は迷惑なの?
- お盆玉のいつからという発祥
- お盆玉の相場はいくらくらい?
- お盆玉は何歳まで渡すもの?
お盆玉はあげるべきですか?

結論から言うと、お盆玉は必ずしもあげるべきものではありません。お盆玉は、お年玉ほど社会に定着している習慣ではなく、近年になって広まってきた新しい文化と捉えるのが実情です。
そもそもお盆は、ご先祖様の霊をお迎えし、家族で供養するための期間です。そのため、お盆玉を渡すという習慣がないご家庭や地域も多く存在します。実際に、ある調査ではお盆玉をあげた経験がない人が8割以上を占めるという結果も出ています。
このように、お盆玉をあげるかどうかは、それぞれの家庭の考え方や親戚付き合いのあり方によって決まるものです。「周りがあげているから」と無理に合わせる必要はなく、ご自身の考えや経済的な状況を優先して判断して問題ありません。
そもそもお盆玉は迷惑なの?

一方でお盆玉に対して、「迷惑だ」「余計な出費が増える」といった否定的な意見があるのも事実です。特に、お年玉に加えて夏にも出費が増えることに、金銭的な負担を感じる声は少なくありません。
また、お盆玉という習慣自体が、企業の商業的な意図によって作られたものだと感じる人もいます。子どもがお金をもらうことを当たり前だと考えるようになるのでは、と金銭感覚への影響を心配する意見も見られます。
ただし、これはあくまで一面的な見方です。祖父母の世代からは「かわいい孫に会える機会に、気持ちを形にして渡したい」という純粋な好意から歓迎されている側面もあります。このように、お盆玉は立場によって捉え方が異なるため、迷惑かどうかを一概に断定することは難しいと言えます。
お盆玉のいつからという発祥

お盆玉という名称が広く知られるようになったのは比較的最近ですが、その原型となる習慣は江戸時代にまで遡ります。
江戸時代の「お盆小遣い」
当時、商家などで丁稚奉公をしていた子どもたちが実家に帰省できるのは、お正月とお盆の年2回だけでした。特に山形地方では、雇い主が里帰りする子どもたちに「お盆小遣い」としてお金や着物などを渡す習慣があったそうです。これが、現代のお盆玉のルーツと考えられています。
現代の「お盆玉」の普及
「お盆玉」という名称を付けてポチ袋を商品化したのは、山梨県にある紙製品メーカーの株式会社マルアイです。2010年頃から販売を開始し、その後、郵便局でも扱われるようになったことで、その名称と習慣が全国的に認知されるようになりました。少子化でお年玉用のポチ袋の需要が減る中、夏にも需要を喚起したいという狙いがあったようです。
お盆玉の相場はいくらくらい?

お盆玉を渡す場合に最も悩むのが金額の相場です。お盆玉はまだ歴史が浅く、お年玉のように明確な相場が決まっているわけではありませんが、一般的な目安は存在します。
ある調査によると、最も多い価格帯は「1,000円~4,000円台」でした。お年玉に比べると、やや控えめな金額設定が主流のようです。関係性や子どもの年齢によって金額を決めるのが一般的で、以下の表を目安にするとよいでしょう。
| 対象年齢 | 金額の目安 | 備考 |
| 未就学児 | 1,000円程度 | 現金の代わりに絵本やおもちゃを渡すのも喜ばれる |
| 小学生(低学年) | 1,000円~3,000円 | 子どもが管理しやすい金額が望ましい |
| 小学生(高学年) | 3,000円~5,000円 | 行動範囲が広がるため、少し高めに設定する人もいる |
| 中学生・高校生 | 5,000円~10,000円 | 部活動や交友関係でお金が必要になる時期 |
| 大学生以上 | 5,000円~10,000円 | あげないという選択肢も一般的 |
Google スプレッドシートにエクスポート
もちろん、これはあくまで目安です。お盆の時期は何かと出費がかさむため、無理のない範囲で金額を設定することが大切です。かわいい孫に対しては、祖父母の財布の紐が緩みがちで、10,000円以上を渡すケースも少なくないようです。
お盆玉は何歳まで渡すもの?

お盆玉を何歳まで渡すかについても、明確な決まりはありません。基本的には、お年玉と同じように考えている家庭が多いようです。
一般的には、高校生まで、あるいは大学生までが一つの区切りとなるでしょう。大学生になるとアルバイトなどで自分で収入を得るようになるため、渡さないという判断も自然です。また、社会人になった子どもには、お盆玉を渡す必要はありません。
最終的には、それぞれの家庭の方針や、子どもとの関係性で判断するのが一番です。例えば、「高校を卒業するまで」「20歳になるまで」といった家庭内のルールを決めておくのも一つの方法です。
お盆玉をあげない人も知りたい渡し方
- お盆玉の書き方と入れ方の作法
- お盆玉は新札を用意すべき?
- お盆玉はいつ渡すのがベスト?
- 現金の代わりにお菓子を渡すのは?
- お盆玉のお返しやお礼は必要?
お盆玉の書き方と入れ方の作法

もしお盆玉を渡すのであれば、相手に気持ちよく受け取ってもらうためのマナーを押さえておきましょう。特にポチ袋の準備やお金の入れ方は、少し気を配るだけで印象が大きく変わります。
ポチ袋の準備
お盆玉は、現金をそのまま手渡すのではなく、ポチ袋に入れるのが一般的です。夏らしいデザインや、子どもが好きなキャラクターのポチ袋を選ぶと喜ばれます。お盆の時期になると、郵便局や文具店、スーパーなどで専用のポチ袋が販売されますので、事前に準備しておくと安心です。
お札の折り方と入れ方
ポチ袋にお札を入れる際は、正しい折り方を覚えておくとスマートです。
- お札の肖像画が描かれている面を表にして、肖像画が右側にくるように置きます。
- 左側から3分の1のところで内側に折ります。
- 次に右側を、折った部分の上に重なるように折ります。これで三つ折りになります。
- ポチ袋の表側から見て、お札の肖像画の顔の部分が見えるように入れます。
宛名と自分の名前の書き方
ポチ袋には、誰から誰へのものか分かるように名前を書きましょう。
- 表面(おもてめん): 渡す相手の名前を「〇〇ちゃんへ」「〇〇くんへ」のように、少し大きめに書きます。
- 裏面(うらめん): 自分の名前を「〇〇おじちゃんより」のように、相手の名前より少し小さめに書きます。
お札を入れる前に名前を書いておくと、お札に筆圧の跡がつかないのでおすすめです。
お盆玉は新札を用意すべき?

お年玉と同様に、お盆玉でも新札(ピン札)を用意するのが望ましいとされています。新札を用意するのは、「この日のために、前もって準備していました」という相手への心遣いや丁寧な気持ちを示すためです。
とはいえ、必ずしも新札でなければマナー違反というわけではありません。銀行の窓口が閉まっているお盆期間中に、急に新札を用意するのは難しい場合もあります。
もし新札が手に入らない場合は、できるだけ折り目の少ないきれいなお札を選んで渡しましょう。シワだらけのお札を渡すのは、相手に失礼な印象を与えかねないため避けるのが賢明です。
お盆玉はいつ渡すのがベスト?

お盆玉を渡すタイミングに、厳密な決まりはありません。親戚が集まる滞在期間中の、都合の良いタイミングで渡せば問題ないでしょう。
一般的には、親戚一同が顔を合わせた初日や、食事などで集まった際に渡すことが多いようです。子どもたちが複数いる場合は、他の子の前でこっそり一人だけに渡すのではなく、全員に同じタイミングで渡すのが配慮となります。
また、別れ際に「また元気に会おうね」という気持ちを込めて渡すのも良いタイミングです。いずれにせよ、子どもの親がいる前で渡すのがスムーズでしょう。
現金の代わりにお菓子を渡すのは?

お盆玉は、必ずしも現金である必要はありません。特に、まだお金の価値が分からない未就学児などには、現金以外のものを渡すのも素晴らしい選択肢です。
現金以外のプレゼントの例
- お菓子の詰め合わせ: 子どもが好きなお菓子を詰め合わせたものは、間違いなく喜ばれます。
- 絵本や図鑑: 夏休みの読書にぴったりの一冊を選ぶのも良いでしょう。
- 文房具: シールやお絵かき帳など、すぐに使えるものがおすすめです。
- 夏らしい遊び道具: 虫取り網や水遊びグッズなど、その場で遊べるアイテムは夏の良い思い出になります。
- 図書カードやこども商品券: 少し大きい子どもには、自分で好きなものを選べる金券も人気です。
現金に抵抗がある場合や、相手に気を使わせたくない場合には、こうしたプレゼントを「夏のご挨拶」として渡すのもスマートな方法です。
お盆玉のお返しやお礼は必要?

自分の子どもがお盆玉をもらった場合、基本的にお返しは不要です。お盆玉は、お祝い事などとは異なり、目上の人から子どもへのお小遣いという位置づけだからです。
無理にお返しをすると、かえって相手に気を使わせてしまう可能性があります。まずは、子ども自身から直接「ありがとう」とお礼を言わせることが最も大切です。そして、親からも感謝の気持ちをきちんと伝えましょう。
ただし、例外もあります。相手にも自分と同じくらいの年齢の子どもがいる場合は、お互いの子どもに同程度の金額のお盆玉を渡し合うのが一般的です。このような状況に備えて、何ももらわなかった場合でも渡せるように、ポチ袋と現金をいくつか準備しておくと、いざという時に慌てずに対応できます。
もし高額のお盆玉をもらってしまい、どうしても気が引ける場合は、後日、お菓子や日用品といった負担にならない程度の品をお土産として渡したり、子どもの写真とメッセージを添えたお礼状を送ったりすると、感謝の気持ちが伝わるでしょう。
結論:お盆玉をあげない選択も尊重
この記事では、お盆玉をあげないという選択肢から、渡す場合の相場やマナーまでを詳しく解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。
- お盆玉は必ずしもあげるべきものではない
- あげるかどうかは各家庭の判断に委ねられる
- お盆玉の習慣がない家庭や地域も多い
- 否定的な意見として金銭的負担や商業主義への反発がある
- 原型は江戸時代の「お盆小遣い」に由来する
- 現代の「お盆玉」は2010年頃から普及した
- 相場はお年玉よりやや低めの1,000円から5,000円が中心
- 渡す年齢に決まりはないが高校生や大学生までが一般的
- 渡す際はポチ袋に入れ、名前を書くのがマナー
- お札は新札か、なるべくきれいなものを用意する
- 渡すタイミングは親戚が集まった時などが良い
- 現金の代わりにお菓子やプレゼントを渡す方法もある
- お盆玉をもらっても基本的にお返しは不要
- 感謝の気持ちを親子で伝えることが最も大切
- お盆玉をあげないという選択も尊重されるべきである